登場人物
「風神の門」の登場人物紹介です。「蛇足」はヒマな方は読んでください(笑)※本ウェブサイトをWindows(Internet Explorer)でご覧になる場合は、文字サイズを「小」(メニューバー[表示]→[文字のサイズ]→[小(S)])にすると見やすくなります。
|
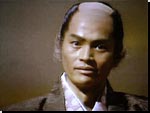
|
|
||||||||||||||||
|
京都所司代。伊賀守。豊臣家や公家に対しての監視および交渉役。駿府の家康や本多正純の意を受けてさまざまな謀略を直接指揮する。大納言晴季に青子の下向を迫り、方広寺焼失や鐘銘文事件、明石掃部の誘き出し、隠岐殿誘拐、大坂城の濠埋め立て、幸村内応の流言など、ほぼすべての陰謀の黒幕。家康の長寿祝いの宴では直前に宴の間を変更し、才蔵たちを窮地に追い込んだ。開戦後、江戸留守居となる俊岳から主を乗り替えた獅子王院を使うが、その功に報いずうち捨てる。
徳川家譜代の家臣である板倉好重の次男として、三河国額田郡小美村(愛知県岡崎市)に生まれる。幼少の頃に出家して浄土真宗の永安寺の僧・香誉宗哲(こうよそうてつ)となるも、父や家督を継いだ弟の討死により天正9年(1581年)還俗して家督を相続。僧あがりの勝重は戦働きはほとんどせず、施政面で活躍する。駿河町奉行・関東代官・江戸町奉行を歴任後、慶長6年(1601年)に京都町奉行・京都所司代に任命され、京都の治安維持と朝廷の掌握、さらに豊臣家と西国大名の監視に当たる。大坂の陣では方広寺鐘銘文事件に一役買い、大坂城に小幡景憲(勘兵衛)らの間者を放つ。大坂の内応者の情報の多くは勝重から駿府へ送られた。真田幸村に対する「東の諜報家」。京都という大坂方の陣地内ともいえる場所で知謀と諜報を巡らし、徳川方の勝利に大いに貢献した。元和6年(1620年)に子の重宗に京都所司代の職を譲るが、その後も京に残り重宗を補佐した。
劇中ではラスボス的な勝重であるが、実際は元僧侶であったためか、無欲公正で所司代としての評判は高く、多くの逸話が残されている。名奉行・大岡越前のエピソードの一部は実際には板倉勝重のものだと云われるものもあるほどだ。弾圧するべきキリシタンにも人道的な処置を取った。キリシタンの女を助けて役人を蹴散らした才蔵は、普通なら鞭打ちの20や30はくらいそうだが、お咎めなしの放免とは勝重の寛大さによるものか。本来世襲制ではない京都所司代の後任を子の重宗が嗣ぎ、立派に職務を果たしている。 とはいえ、風神の門では立派なラスボス。史実では70歳前後であった勝重は、寺田農によって壮年のダーティーな悪役として描かれている。その仕業に敵味方を問わず煮湯を飲まされた者数知れず。初登場の超尊大な態度は忘れがたい。また俊岳に対して「幸村を事前に殺せなかった、それが悔いといえば悔いでございましょうのう」というセリフには、日本中から「お前が放っておけってゆーたやん!」というツッコミがあったはず。全国に支部を持つ「獅子王院同盟」からは刺客が放たれたという噂もある(噂です)。しかし、主人公と直接顔を合わせないラスボスもめずらしい。というか主人公はこのラスボスから直接は被害を受けていない。青子を持ってかれたことと、嫁さんの父親が苛められたくらいか。豊臣恩顧の者にとってはまさに刺客を放ちたいくらいだろうが、才蔵は幸村に心服して大坂に付いただけなのでたいして恨みはないのか。もっとも板倉の方は才蔵に「存念」があるらしいので、しばらくは京都に近づかないのが無難…。 |
|||||||||||||||||
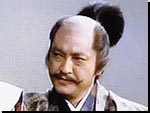
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
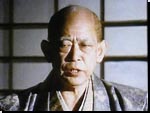
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||

|
|
|||||||||||||
|
現在の伏見城(伏見桃山城)は、文禄元年(1592年)に豊臣秀吉が築城した伏見指月城が文禄5年(1596年)の伏見大地震で倒壊した後、新たに桃山(現在の木幡山)に築城されたものである。慶長2年(1597年)に完成し、秀吉は秀頼を伴って入城した。翌年の慶長3年(1598年)に秀吉が没し秀頼が大坂城に移ると、徳川家康が入城し居城とした。慶長5年(1600年)、石田三成に攻められ落城。留守居の鳥居元忠は城と運命を供にした。その後家康は城を再建。慶長8年(1603年)、家康はこの伏見城で将軍宣下を受け、慶長10年(1605年)には秀忠、元和9年(1623年)には家光が同じく将軍宣下を受けた。しかし寛永2年(1625年)、廃城のためすべて取り壊される。
伏見城址は、現在は伏見桃山陵(京都市伏見区桃山町)として天皇陵に転用されている。明治天皇を祀った伏見桃山陵(伏見城本丸跡)、昭憲皇太后を祀った伏見桃山東陵(伏見城名護屋丸跡)があり、その北端には桓武天皇陵がある。 石田三成が挙兵すれば、まず伏見城がその標的になることは、会津上杉征伐に向かった家康(忠政=俊岳も同行)も留守居の元忠も予見していたと云われている。そして2人とも落城は覚悟の上だったようだ。だったらたとえ妾腹といえども子どもは避難させようよ、俊岳さん。もしかして忘れてた? |
||||||||||||||
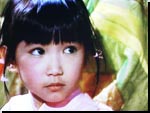
|
|
|||||||||||||
|
お国の回想シーンに登場。かわいいです。薄情な俊岳に怒った甲賀者が生駒山に連れ去ったのもわかります。
原作では、お国の父は豊臣秀吉の忍びであった甲賀の望月喜太夫。母は秀吉の侍女・幾野。小若とは腹違いの姉妹。喜太夫は伏見城下の拝領屋敷にいた頃、密かに幾野と通じ懐妊させた。幾野はすぐに宿下がりし、父親の名を明かすことなくお国を出産後病没。幾野の父の祐筆・佐治助右衛門は自分たち夫婦の子としてお国を育て、助右衛門が死んだ後、お国は助右衛門が懇意にしていた大野修理の屋敷に引き取られ、隠岐殿の侍女となった。 劇中では、伏見城つながりで俊岳の娘ということになったのか。ところで、お国は才蔵に自分は伏見城で生まれたと告白しているが、実際にはこれはありえない。お国は1594生まれ。伏見城は「お国の母」の項で書いた通り2つあり、ひとつめの伏見指月城がお国が生まれた年に完成し、秀吉が入城している。家康の家臣であった俊岳の父・鳥居元忠が、ましてや侍女を連れて城に入れるわけがない。この時元忠は、下総矢作(千葉県佐原市)に4万石の矢作(やはぎ)藩を知行していた。仮にお国が1596年生まれ(「お国」の項参照)だとしても、この年にはまだ伏見城は秀吉の居城であった。ちなみにこの年の閏7月、伏見大地震が起き、伏見指月城は倒壊の憂き目をみる。お国がいたふたつめの伏見桃山城が築城されるのはこの年であり、完成は翌年である。家康が居城とするのは秀吉の没した1598年のこと。お国は既に5歳になっている。お国の母が本当に元忠の侍女であるなら、お国が生まれたのはおそらく矢作城であろう。「親子の名乗りはできない」と俊岳は言っているので、鳥居親子が家康とともに伏見城に入る際、正室のいる矢作城には置いていけず、やむなく伏見城に連れて行ったのかもしれない。祖父と父についていかず母子で矢作城に残っていれば、母親が死ぬこともなく、お国は大名の娘としてそれなりの一生を送れたかもしれない。当然、才蔵と出会うこともなかったが。 堀越恵里子は、1978年の大河ドラマ「黄金の日日」で、のちの呂宋助左衛門(市川染五郎/現・9代目松本幸四郎)の妻となるはずだったききょう(竹下恵子)の子役を好演。風神の門出演の2年前で、もう少し小さい女の子の役だが、これもめちゃめちゃかわいい。黄金の日日では、竹下恵子は堀越恵里子扮する幼いききょうの母親しま役と、成長したききょう役を演じた。つまり「母親に瓜二つ」というわけ。お国の母親役も小野みゆきが演じたらおもしろかったかもしれない。 |
||||||||||||||

|
|
||||||||||||||||
|
江戸幕府の開祖。関ヶ原の戦いで石田光成軍を敗り、征夷大将軍になる。慶長10年(1605年)に息子の秀忠に将軍職を譲り、自らは「大御所」として二元政治を行い、徳川政権安泰のために豊臣家を潰そうとする。才蔵は幸村の命で家康暗殺のために駿府へ赴くが失敗。その後、田中城、名古屋城でも試みるがことごとく失敗する。
戦国時代に三河の小大名として生まれ、幼年を尾張、駿府で人質として過ごす。桶狭間の戦い後、織田信長と結び三河国を統一。信長の死後、秀吉に従い五大老筆頭となるが、秀吉の死後、関が原の戦いで石田三成に勝利し、事実上政権を執る。
家康は戦略家でもあるが、謀略家としての悪名が高い。秀吉の死以降大坂の陣までの間には、多くの謀略に長けた側近たちを用い豊臣家を滅ぼそうとした。徳川家繁栄のためには手段を選ばなかった家康だが、自家のためだけに豊臣家を滅ぼしたのではないようだ。大坂の陣の翌年、家康は死去するが、彼は以下のような遺言を残している。
わが命旦夕に迫るといへども将軍斯くおはしませば天下のこと心安し されども将軍の政道その理にかなわず億兆の民艱難することあらんには たれにても其の任に代らるべし 天下は一人の天下にあらず天下は天下の天下なり たとへ他人天下の政務をとりたりとも四海安穏にして万人その仁恵を蒙らば もとより家康が本意にしていささかもうらみに思うことなし 元和2年(1616)
──もはや我が命は終わりに近づいたが、将軍(秀忠)が立派に政道を行っているので天下のことは心配ない。しかし、将軍の政道が道を外れ、万民が苦しむことになるようなことがあれば、誰にでもその座を代えるがよい。天下は(将軍)一人のための天下ではない。天下は万民のための天下である。たとえ誰が天下を治めようとも、四海安穏であり万人が幸せであるのなら、もとより家康の望むところであり、いささかも恨みに思うことはない。
入江正夫(現在は、入江英義)は、劇中第15回で家康を演じているが、第11回で侍、第14回で影武者を演じている。おそらく第11回は顔の映らない家康、第14回の影武者は才蔵に殺された役であろう。とすると才蔵が殺したのは影武者…???
|
|||||||||||||||||

|
|
|||||||||||||
|
宗次、仁左衛門。討ち取られる際、幸村は名乗らなかったので、あとで自分が討ち取った首の正体を知った久作は、思いがけない金星に歓喜したともビビったとも伝えられている。しかし、名将・真田幸村を討ち取ったというのに、その後の扱いはあまりよくなかったらしい。家康・秀忠の前で行われた首実検で、久作は幸村と何合か斬り合いをしたなどと言い家康の勘気に触れたとか、「拾い首だろう」とか「影武者だ」とか言われて褒美をケチられたなどと云われている。どれもさだかではない。
さんざんな久作だが、国に帰ると西尾家の菩提寺である孝顕寺に幸村の供養のために首塚を建立したのだそうだ。現在、その首塚は福井市立郷土歴史博物館に「真田地蔵」として展示されている。名将に敬意を表したのか、それとも後世に幸村を討ったのは自分だと伝えたかったのか、それもさだかではない。 |
||||||||||||||
Copyright © 2005-2016 風神の門の蛇 All Rights Reserved. ※禁転写(60324)
