登場人物
「風神の門」の登場人物紹介です。「蛇足」はヒマな方は読んでください(笑)※本ウェブサイトをWindows(Internet Explorer)でご覧になる場合は、文字サイズを「小」(メニューバー[表示]→[文字のサイズ]→[小(S)])にすると見やすくなります。
|

|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
京の武具屋、閑古堂の主人。実は堺の大商人「堺屋」の大番頭。閑古堂を拠点にして、密かに京の大坂方隠密の活動を支援している。そうとは知らず刀を求めた才蔵に銀5匁の刀を銀4匁で売った。家康暗殺の武器を作った伊賀の松助に礼金を遣わしたり、隠岐殿救出の際の伊賀者への礼金を捻出するなど、金銭的支援が大きい。獅子王院によって看板娘・小若を失うが、のちに分銅屋を失った信乃を引き取る。開戦後、堺屋の主人・堺屋利兵衛の命により閑古堂を閉じて堺に戻るが、利兵衛の徳川方への寝返りを知り、堺屋辞す。その後大坂に店を構え、続けて幸村らを支援した。

若者ばかりの大坂方隠密メンバーのご意見番といった風格がある。大店「堺屋」をバックにしているだけあって、金銭面の援助は惜しみがない。また、閑古堂に刀を売買にくる牢人をそれとなく大坂方にヘッド・ハンティングするなど、各方面に活動している。才蔵も閑古堂で刀を求めた際、牢人と勘違いした治作にヘッド・ハントされた。
利兵衛の先代の頃から堺屋に奉公しているらしく、太閤秀吉の治世を「虹のような時代」といい、深い恩義を感じている。よって利兵衛の徳川方への寝返りが許せず、長年勤めた堺屋をあっさり辞めてしまう。その後すぐに大坂で商売を始めてしまうところはさすが年季の入った堺商人といったところだろう。温厚で頼りになる人物であるが、敵方に寝返ったとはいえ、旧主人の商売を邪魔して商品を奪うなど、怒らせるとコワイ人かも。 大坂城落城後は、大坂に開いた新しい店で信乃と商いをしていくようだ。才蔵に新しい店を手伝ってほしいと、またしてもヘッド・ハントをかけるが、才蔵はどちらかというと遊女屋の亭主の方がいいらしい。しかしお国が「それだけはお止めください」と発言しているので、たとえ大坂に戻って菊千代の遊女屋の(居候という名の)亭主におさまろうとしても、お国に耳を引っ張られて治作の店に連れて行かれそうだ。 稲葉義男は「七人の侍」の「五郎兵衛」役であまりにも有名。「孫八」役の北見治一とはわずか半月ちがいの同じ大正9年生まれ。数々の名脇役をこなしたが、1998年4月20日に没している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||

原作の小若は甲賀望月家の息女で、お国に代わって才蔵と駿府への旅をするが、こちらの小若は商家のかわいい看板娘だ。才蔵に「かわいいなぁ」と言われたりしている(その後ひっぱたいているが)。佐助が櫛を贈ったり、デートに誘ったりして猛然とアタックしていた。小若ももらった櫛を髪にさして水鏡に映したり、まんざらでもない様子。才蔵に幸村の素性を聞かれて突っぱねたり、蝮の脅迫に耐えたりなかなか気丈な娘であったが、やはり忍の拷問には耐えられなかった。秘密を守るために松助によってとどめを刺されてしまう。小若の死は、才蔵には佐助の想い人を死なせてしまったとして、お国には自分が俊岳や獅子王院に情報を漏らしたことによって死なせてしまったとして、傷を残すことになる。登場人物中でもっとも悲惨な運命を負わされてしまったが、今は天国で佐助と仲良く笑っているかもしれない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
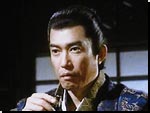
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
堺の商人「堺屋」の主人。大坂方を支援して、大坂城と京の隠岐殿の連絡役や物資の調達をしていたが、時代の潮流が徳川方に向いていると判断して寝返る。その際まず、京の大坂方隠密の拠点となっていた閑古堂を閉め、大番頭・治作を呼び戻した。さらに大坂城の濠を埋める鍬・斧などを板倉勝重に納め、才蔵から預かった青子を差し出すことを申し出る。これには才蔵の怒りを買い、治作が豊臣家の恩を説くが「商人は利を求めねばならん。これからは徳川の天下、商いのできる相手を選んでなぜいかん。青姫とて儂には商いの品」と言いはなつ。

よく才蔵が斬らなかったなあと思うのだが、治作の主人なので遠慮したのだろうか。もっとも、その後治作はあっさり辞表を出したので呆気にとられていたが。
商人の町「堺」は、応仁の乱(1467-1477)以降の戦国時代に海外貿易で莫大な財をなした豪商たちによって、もっとも栄えた。その勢いは会合衆などの運営による自治都市として、時の権力者にも一目置かれていたほどだ。また戦乱から町を守る濠や水路を巡らせた環濠都市は、イエズス会の宣教師によって「東洋のベニス」としてヨーロッパ世界にも紹介されている。「堺」という地名は、摂津、河内、和泉の三国の境(さかい)に発展した町という意味で付けられたといわれる。織豊政権によって「自治都市・堺」は解体されるが、それでも堺は権力者たちと結びついて富を蓄積していく。しかしやがて、より地の利のよい大坂に経済の中心は移り、町は大坂夏の陣で大野治胤によって焼き払われてしまう。それでも堺の商人たちはたくましく復興する。治世や権力者が代わってもそれに順応する能力を持った者が商人なのだろう。 風神の門の舞台の半世紀ほど前(織豊政権あたり)の堺の商人としては、今井宗久、津田宗及、千利休、納屋(呂宋)助左衛門などが挙げられる。彼らに関しては同NHK時代劇「黄金の日日」をご覧いただきたい。1978年放送の大河ドラマであるが、スタッフがけっこう被っているので、風神ファンにはなかなか見応えがあると思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2005-2016 風神の門の蛇 All Rights Reserved. ※禁転写(61014)












